電動列車

今日は友人と、友人のお子さんと遊びました。
友人のお子さんはもうすぐ4歳です。
その子が赤ちゃんの時に会ったことはあるのですが、3年ぶりぐらいで、「初めまして!」から始まりました。
ショッピングモールでいっしょにランチを食べて、子供の遊び場で遊んで、アイスクリームを食べて、「列車に乗ろう」という話になりました。
列車といっても電動列車で、ショッピングモールを5~10分で一周してくるものです。
上に載せた写真とは少し違い、もう少し大きく、乗るところは箱型のものがいくつか繋がっており、レールのないものです。
子供用の列車に乗るという経験があまりないので、わたしはためらってしまいました。
5分ぐらいなら木陰で待ってようかなと思いました。
そういう、つまらない大人の考えがよぎりました。
本当につまらない考えだったなと思います。
友人が「チケットがあるから一緒に乗りましょう!」と言ってくれて、一緒に乗りました。
帰ってきて、あのとき一緒に乗って本当に良かった、と心から思います。
もうすぐ4歳というこのタイミングで、一緒に列車に乗らないと、同じタイミングは二度と来ません。
狭い狭い箱の中で膝をくっつけて、電動列車でショッピングモールをまわることができて、楽しかったです。
子供は成長が早いので、時間の一瞬一瞬が宝物で、同じ時は二度と経験できないものが多いです。
大人の論理で子供に向き合うのは完全にやめなければならないな、と思いました。
この子に次会うときはこの子がもう少し成長しているので、その時にも新しいことを一緒にできればいいなと思います。
アンカー
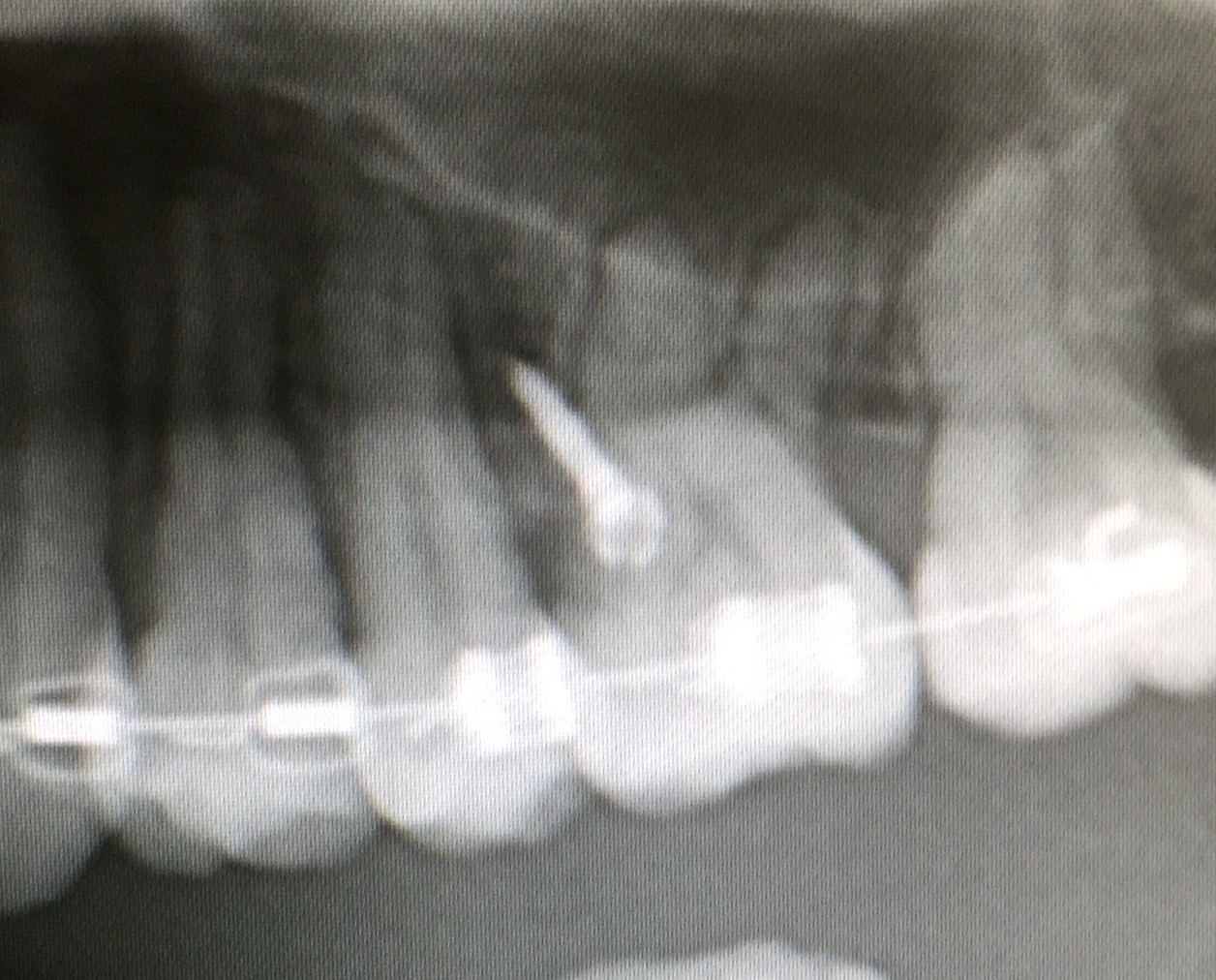
昨日、歯医者さんでアンカリングしてもらったので、アンカリング記念にアンカーの記事を書きます。
これはわたし自身のレントゲン写真です。
真ん中にみえる釘のようなものは、矯正歯科で用いるスクリューです。
このスクリューは歯槽(骨)に刺されていて、アンカー=錨として機能します。
スクリューに向かって歯がダイナミックに動きます。
アンカーとトリガーはコーチングではあまり使わない用語ですが、説明します。
アンカーは「錨」であり、心の状態としては「記憶しておく」状態を指します。つまり、いつでも引き出せるように人間の脳内に埋め込んだ「ある心理状態もしくは体感状態」のことをアンカーといいます。
そして、その心理状態を引き出す「引き金」の役割を果たすのがトリガーです。
良い例があまり浮かばないのですが、コーチングと繋がるような例をあげると、「ゴールのイメージ」と「アファメーションを書いた紙」がアンカーとトリガーに近いのかなと思います。
わたしはアファメーションをプリントアウトして冷蔵庫に貼っています。
アファメーションは最初のうちは読みますが、暗記してしまうと文字を読まなくても紙を見た瞬間にイメージがわくようになってきます。
たとえば、このトリガーとして機能している「アファメーションを書いた紙」を、もっと接する頻度の高いものに変えることが可能だと思います。
髪を触る、歯を磨く、顔を洗う、などにより「ゴールのイメージ」がぱっとわくようにすると、アンカーを呼び起こす頻度が高くなりゴールを視覚化する頻度が高くなることになります。
少しわかりにくい説明になってしまいましたが、わかりにくい理由はわたしの理解がまだ未熟だからです。
次にスクリューが入ることがあったときに、「続 アンカー」の記事を書けるよう、理解を深めたいと思います。
キーホルダー
キーホルダーから鍵が外れなくなり、うんともすんとも言わなくなっていました。
昨日、靴の修理屋さんで大きなペンチを使って壊していただきました。
引っ越しをしたいという気持ちもあり、鍵をキーホルダーから外したいと、心のどこかでずっと思っていて、ついに実現しました。
ペンチで切っていただいた瞬間、かなりすっきりしました。
「鎖からようやく放たれた」という印象です。
みなさんも、心のどこかで引っかかっていることが何かあるかもしれません。
潜在意識にうまくおとしておけば、タイミングよく実現します。
でも、意識でコントロールしてすぐに実現できるならば、行動してください。
いま、鍵には鎖ではなくクマのキーホルダーを付けています。
もの食ふ人々

東京に上京してから受けたカルチャーショックのひとつについて、考えていました。
東京では、一人で歩きながら、もしくは一人で電車の中で、パンやお菓子を食べている人をよく見かけます。
最初見たときは、かなり驚きました。
わたしにとっては、地方ではあまり見ない光景だと感じました。
先日、朝の比較的混んでいる電車の中で、カバンの中にあるお菓子の袋からゴソゴソとチョコレート菓子を食べている人を見かけました。
朝の7:30に、混んだ電車の中で立ったまま、なぜチョコレート菓子をむさぼる必要があるのか。
これは日本社会の仕掛けた罠が、特に東京において顕著に現れているものと考えています。
食欲は人間の煩悩のひとつであり、なくては生きることができません。
しかし、食欲というのはお腹がすいたら食事をする、それだけです。
東京における食欲の異常な表現のされ方は、わたしにとっては違和感を感じざるを得ません。
では、この罠は何か。
苫米地英人博士も多数の著書で指摘されているように、(他の国に関しては知識がないのでなんとも言えませんが)日本社会は「飢餓への恐怖」を人々にうえつけることで、恐怖をもちいて人々をコントロールしているように見えます。
その表現型として表れているものの一つとして、上記に書いたような異常な食行動があるのだと考えています。
おそらく、駅のホームでパンを食べながら歩いている人たちは、特別なにも考えていません。
食行動がどうのという以前に、「なにも考えていないこと」が大問題だと、わたしは感じます。
「ハウルの動く城」
昨日、宮崎駿監督の「ハウルの動く城」を観ました。
数日前からYouTubeで宮崎駿監督のインタビューを見ており、宮崎駿監督の世界を(再度)みたいと感じ、持っていたDVDを観ました。
新しく感じたことがたくさんありました。
みなさんと同様に、わたしも日々変化しています。
今日のわたしは昨日のわたしとは異なります。
「ハウルの動く城」で新たに感じたこと、スコトーマが外れたことがたくさんあったので、それについて少し書こうと思います。
宮崎駿監督が意図しているところと、わたしが感じたことは違っているかもしれないし、違っていて良いと考えています。
宮崎駿監督の意図は確実に存在します。それと並行して、映画を観るたび、人に「何か」を感じさせることが、宮崎駿監督の意図のような印象も受けます。
昨日観た中で最も印象に残ったシーンのひとつについて書きます。最後のあたりのシーンです。
ソフィーがハウルにカルシファーを戻し、ハウルが目覚めたとき、ハウルは身体の重さをうったえました。
そのときソフィーが「心って重いの」と言っています。
「心って重いの」
そう、心は重いのです。
コーチングでは、脳=心=マインドですが、心を見せろといって脳をみせようと考える人は少ないと思います。
なぜならば、脳は物理空間の存在であり、心とマインドは情報空間の存在なので、脳をみせることは心やマインドをみせることにならないからです。
存在している場所が違います。
かといって、わたしたちの心やマインドは確実にあります。
その存在は物理空間では見えないけれども、確実に「重い」ものです。
まさに、心って重いのです。
reader読者登録
ブログ購読をご希望の方はこちらからご登録ください。
