続「幸福の計算式」
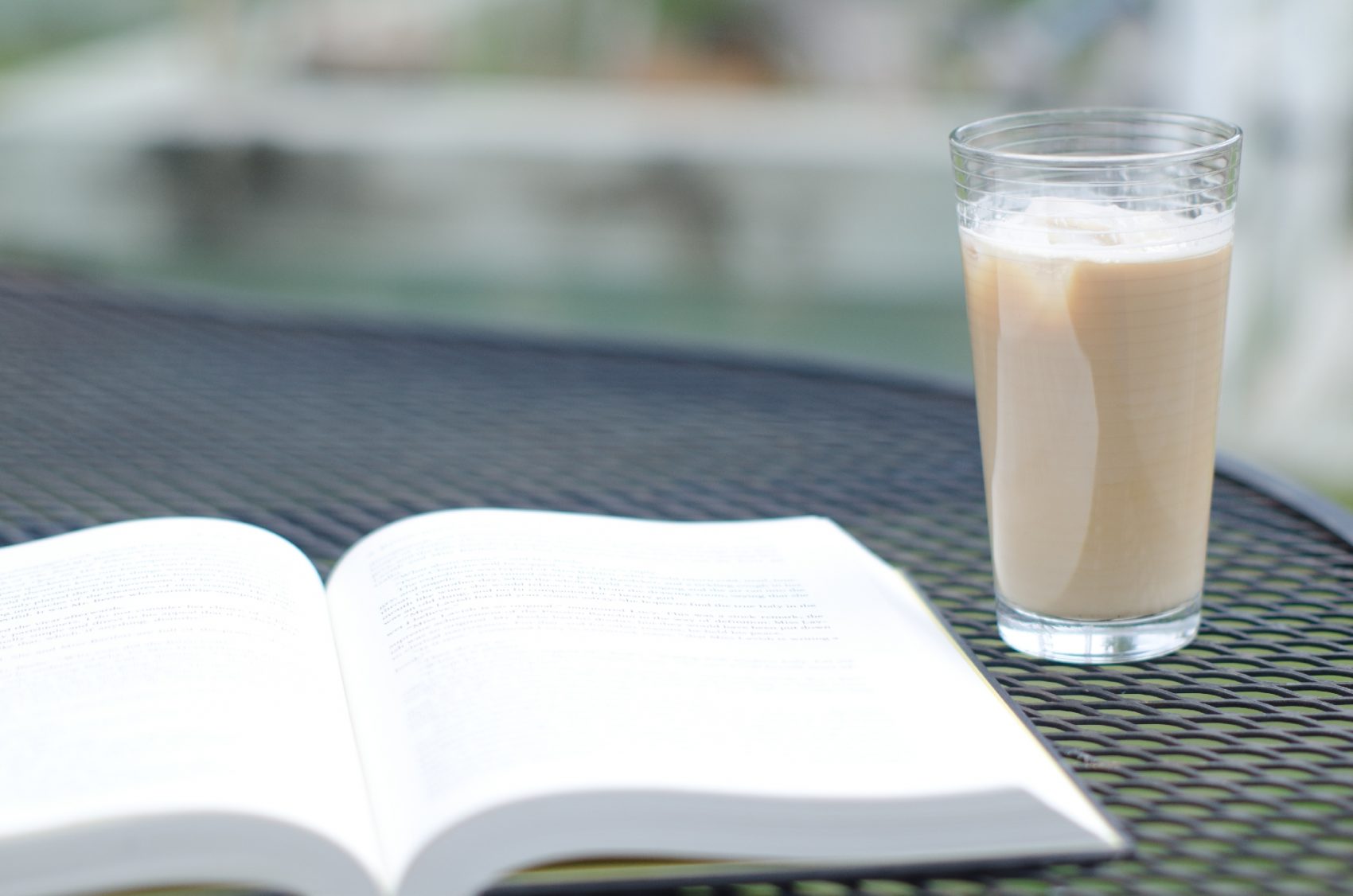
ニック・ポータヴィー著「幸福の計算式」より、引き続き引用します。
わたしのこの本の一番大好きなところを引用させて下さい。
最後の章、第11章です。
「幸福に関する研究は確かに、『幸福な人生とは何で成り立っているのだろうか?』という私の疑問の多くに答えを見いだす助けになった。だから、私はこうした発見に常に誇りをもっている。だが、タイにいる祖母に喜んでもらえると信じて、自分の生業を話そうと決めたのは、ごく最近のことだ。私は彼女のもとを訪れ、お金は人を幸せにするが私たちが考えているほどではないということ、人はいい出来事に慣れるが不幸な出来事にも順応するということを話した。また、幸福に関する最近の発見、つまり、どんなことでも、それについて考えているときには、その重要性を過大評価してしまうという人間の傾向についても話した。私の祖母は敬虔な仏教徒であり、学校教育を受けたことのない元農民であり、歳は90で、微笑むたびに『スター・ウォーズ』に出てくるヨーダのように見える。そんな祖母は私の話を聞いて、少し体を傾けながらこうささやいた。『私がまだ知らないことを教えてちょうだい』 おかしなことだが、まったく彼女の言うとおりなのだ。」
この後に、シッダールタ、つまり釈迦の話が続く。
わたしはこの本におけるこの第11章が、最高にクールだと思います。
読むたびに90のクールなヨーダが目の前にいるように感じます。
「幸福の計算式」
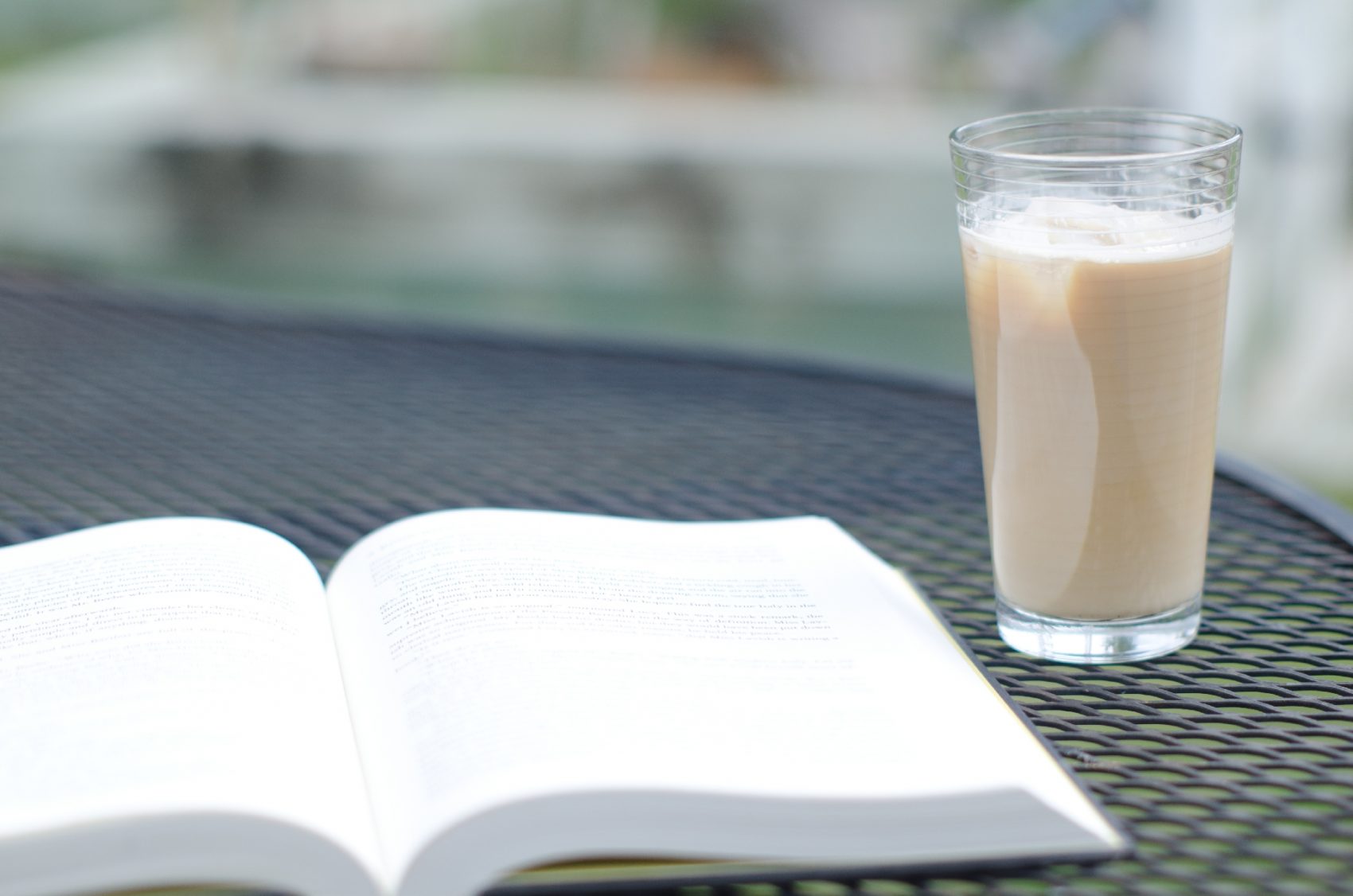
ニック・ポータヴィー著「幸福の計算式」はわたしの好きな本のひとつで、久しぶりに少し読んでみました。
第一章より引用します。
「幸福の計算式ー私たちは、これをずっと考え続けている。幸福の計算式を作る科学的な方法がもし本当にあったとしたらどうだろう?人生のあらゆる出来事に対する典型的な人間がもつ感情をある程度正確に測り、研究することができたなら、そして、それらの出来事が幸福度に及ぼす平均的な影響をまとめた完璧なガイドブックを書けたら?」
「お金は私たちを幸せにするだろうか?もしそうなら、どのくらい幸せになれるのだろうか?あるいは、お金で幸せになれないのなら、それはなぜだろうか?独身でいるよりも結婚したほうが幸せなのだろうか?もしそうなら、どのくらいの間、幸せでいられるのだろうか?離婚はどうだろうか?子どもをもてば幸せになれるだろうか?仕事はどうだろうか?愛する人が死んだら、どのくらい不幸になるのだろうか?そして、もしそうした悲しみを埋め合わせたいと思ったら、いくら必要なのだろうか?いくらあれば子どもや愛する人の死を忘れることができるだろうか?友情にはどのくらいの価値があるだろうか?今もっと幸せだったら、もっと生産的で寛容な人間になって、もっと長生きできるのだろうか?こうした疑問に対する答えの中には満足できるものがあるだろうか?そして、もっと大事なことだが、それによって私は決断の仕方を変えることができるのだろうか?また、国家は国民をもっと幸せにする努力をするべきだろうか?」
苫米地式コーチングのコーチが何を言い出すのかと思われるかもしれませんが、今でもとても興味深い本です。
この部分を読むだけでも、ニック・ポータヴィー氏がどれだけ深く人間の「幸せ」について興味があるのか伝わると思います。
リチャード・イースタリン、ダニエル・カーネマン、アンドリュー・オズワルドなど有名な経済学者や心理学者の研究を交えながら、「幸せ」について追及しようとしています。
本の中でいくつか計算式が出てきます。
値段をつけるべきでないものと思われるものに、値段をつけようとトライしようとしており、是非ではなく著者の好奇心が純粋に面白いです。
計算式の計算結果も興味深いです。
おそらく、訳者である阿部直子さんの訳も絶妙なのだろうなと思います。
今回の記事はここまでにしますが、幸福に関する研究はこれまで多くなされており、今でも幸福に関する本はどんどん世に出てきています。
つまり、人々は幸福になる方法を知りたいと、ずっと思い続けているという事実が存在します。
この事実について、わたしも考えます。
みなさんも考えてみてください。
オレンジ色と緑色

今日はセミナーをさせていただきました。
当初予約していた部屋があったのですが、隣の部屋があまりに素敵だったので、急きょ変更してもらいました。
窓際にはソファがあって、窓から木々が見えていて、晴れていたのでとても気持ちが良かったです。
今日は、内容の抽象度をどのあたりに設定するのがベターなのか考えながらお話をさせていただきました。
学生の頃に学習塾の講師をしていたことがありますが、学習塾ですと抽象度の上げ下げをする必要はあまりなく、テキストに沿って学年に応じた内容の授業をします。わたしにとっては平面的なイメージです。
コーチングのセミナーは、わたしから見ると3次元の立体構造に見えます。
抽象度の高さと、お伝えする幅など、その時に応じて3次元の中をあちらこちらへ動くような印象があります。
必ずお伝えしたいと思うkey wordがいくつかあって、3次元の中にそれらのwordをどのようにうまく入れ込んでいくか、考えながらお話をさせていただきました。
音楽を奏でるのとは少し異なりますが、立体構造を作るようなイメージがあるので楽しいです。
しかも、これは一人でする作業ではなく、聞いてくださっている方々と一緒に作るものです。
昨日今日と、多くのことを学ばせていただき、素晴らしい連休となりました。
こうやって改めてホワイトボードを見てみると、珍しいオレンジ色と緑色を使いたかったな、と感じます。
5色もあったのに、この2色がスコトーマ(盲点)に入ってしまっていた気がします。
次回はオレンジ色をベースに使いたいなと思います。
ドリームリフター

苫米地英人博士の著書の中で、「親は自分の子供のドリームキラーでもドリームサポーターでもなく、ドリームリフターになるのが良い」
と書かれている本があります。
ドリームリフターとは何か、考えていました。
親が自分の子供に対してドリームキラーになってはいけないのは、みなさんご存知かと思います。
かといって、親が自分の子供のドリームサポーターであろうとすると、親の価値観や意図が、子供の未来選択に入ってくる可能性があります。そういった意味で、ドリームサポーターであってもいけないということになります。
ドリームキラーでもなく、ドリームサポーターでもなく、あらゆる選択を自由にできる環境を整え、選択に対して評価をしないのが、ドリームリフターの役割だと思います。
そう考えると、自分の子供に対してドリームリフターで居続けるほうが、ドリームサポーターでいるよりも難しい印象を受けます。
なぜなら、親の価値観をもって限られた選択肢を準備して、その中から子供に選ばせる方が、親にとって遥かに楽だからです。
わたしはコーチなので、ドリームサポーターでいるためのトレーニングを受けています。
クライアントは大人であり、もしくは、年齢的に子供であるとしても自分の子供ではないので、コーチはドリームサポーターの存在でいるのが自然です。
ただ、最近感じるのが、わたしの大切な友人たちはわたしにとってドリームリフターのような存在である人が多いです。
つまり、ドリームキラーではないし、ドリームサポーターというわけでもないけれど、なにも評価をせずにただ応援してくれている、そういう友人が多いです。
逆の視点からみると、ドリームリフターのような友人に対しては、わたし自身もドリームリフターであるような気がします。
お互いがお互いのドリームリフターでいられる関係は素晴らしいと思います。
もしかしたら、近いしい人に関しては、ドリームリフターでいる方が自然なのかもしれません。
みなさんも、近しい人に対してはドリームリフターでいる、という選択肢があることを一度じっくり考えていただければと思います。
「ODYSSEY」
映画「ODYSSEY」を観ました。
Ridley Scott監督、Matt Damon主演の映画です。
簡単に説明するのは難しいのですが、火星に一人取り残されたMark Watneyが孤独の中どのように生き、地球の人間とMark Watneyの仲間がさまざまな判断をしながらどのように彼を救出するか、描かれた映画です。
宇宙を舞台にする映画はたくさんありますが、宇宙から地球を見たり、地球から宇宙を見たり、さまざまな視点の置き方があります。
ODYSSEYでは宇宙からの視点が多い印象を受け、地球が国境を超えて一つになっているように見えました。
Mark Watneyが帰還したのち、Candidate Programの生徒に講義をします。
その時のセリフが印象に残ったので、書きます。
英語で表記しないとどうしても伝わらない部分があるのですが、英語を確実に聞き取ることができなかったために日本語訳を書きます。
「まず始めるんだ。問題を1つ解決したら次の問題に取り組む。そうして解決していけば帰れる。」
「You just begin.」という力強い言葉から始まるこのセリフは、宇宙空間でのproblemに対してのみならず人生における問題のsolutionにおいても同じことだと感じました。
reader読者登録
ブログ購読をご希望の方はこちらからご登録ください。